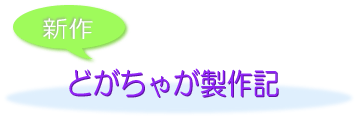 Vol,2 |
 |
原形の芯となるカットした木に、石粉粘土を定着させるために、園芸用の生地ではなく、穴をあけることにしました。 こうしたやり方をするのは初めてですが、どうなんでしょうね、と聞かれても困りますよねぇ。 エポキシで固めてありますから、ドリルでも結構穴をあけるのが大変でした。 穴の間隔は 「だいたいこんなもんかな」 程度です。 あまり深く考えずにぎゅーんぎゅーんって穴を開けていきます。 |
| ここはちょっと丁寧な仕事ぶりです。 そうでもないかな。 石粉粘土に少し水を加えてよく練っております。 これは芯の木によく定着させるためですね。 粘土をこねるときの感触って、本当に気持ちいいですよねぇ。 子どもの頃から大好きです。 作るよりもこねる方が好きだったくらい。 指と指の間からむにゅっと出てくる感触がたまりません。 しかし仕事ですからこねて遊んでいるわけにはいきません。 若干遊んだだけで次の作業へ。 |
 |
 |
最初は芯に定着をさせることが目的ですから、親指であけた穴に押し込むようにして、こすり付けていきます。 ところがエポキシで表面が固められていますから、なかなかうまく表面に粘土が付きません。 「エポキシで固めたことが裏目に出たか?」と思ったけれど、こんなときに浮かぶ言葉が、いつも私を落ち着かせてくれます。 「まぁ、なんとかなるよ」 いい言葉ですねぇ。 ポール・マッカートニーのようにマリア様が来て、「Let it be」 とはささやいてくれませんが、この 「なんとかなるさ」 にどれだけ助けられたことでしょう。 事実なんとかなっちゃうし、なんとかしちゃいますからね。 |
| 全体に薄く粘土を塗りつけたら、ここでいったん乾燥させます。 これが下地となるわけですね。 この上に石粉粘土で肉盛りをしていきます。 今回はエポキシで固めてありますから、粘土の乾燥によってそったりゆがんだりすることはありませんが、木に粘土を付けていく場合、粘土が乾燥したときの収縮で、木がゆがむことがあります。 そうしたときにはゆがまないように、平らな板に固定して乾燥させるといいですね。 |
 |
 |
2〜3日置いて乾燥させたら、乾いた粘土の表面に水をつけて、石粉粘土をこすり付けるように肉付けしていきます。 いきなり厚く盛り付けますと、あとではがれてきますから、少しずつ丁寧に塗りつけていきます。 こうしたところが大切で、時間を惜しんで早く盛り付けようとしますと、あとの作業に影響してきますから、丁寧にしっかりと下地の粘土にくっつけていきます。 |
| ある程度粘土を盛り付けたら、また乾燥をさせます。 もちろんこの段階ではきれいに形作ったりしません。 まだ下地のうちですね。 今はまだ太陽の日差しが強くないからいいですが、夏に粘土を乾燥させる場合は、直射日光は避けたほうがいいですよ。 表面が先に固まって、太陽の熱によって粘土の中の水分が膨張して、表面に亀裂ができてしまうことがありますし、膨張した状態で固まった粘土は、水分が乾燥したあとスポンジ状になりますから、強度が足りなくなります。 基本的には日陰干しするといいですよ。 この状態でまた数日間乾燥をさせます。 |
 |
 |
借りている家は山の南斜面に建っているので、天気がいい日には真冬でも結構暖かいのです。 ですから原形を削ったり、ラッカーを塗ったりする作業などは、こうして外で景色を眺めながら、いろんな考えごとをしながらすることが多いですね。 こんなふうに青空の下で手を動かしていますとね、ストレスが吹っ飛びますよ。 上空をトンビがピーヒョロロと飛んだりして、のどかでいいんです。 オオカタがハトを襲うのを見たことがありますし、目の前の休耕地をシカが走って行ったこともありましたね。 そうだ、親子のシカがぴょんぴょん跳びはねながら逃げて行ったこともありましたっけ。 無心に手を動かしている時間が、子どもの頃から大好きなのです。 好きなことをしていたら、今の仕事につながっていたのですね。 われながらのんきでいいと思いますな。 ははは。 |
| ご覧いただいて、私が特別に高度な技術の持ち主でないことがおわかりいただけたでしょ? こんなんでも20年間やってこられたんですから、みなさん自信がついたと思います。 なんてすばらしいプロからの励ましだろう!(あきれ気味) |